カテゴリ:災害等支援活動
おしらせ■10/13 防災学術連携体 第26回Web研究会 こども環境学会災害復興支援部会
こども環境学会会員および関係者の皆様
※お申込みは必ず事前にこちらからお申込みください。
https://ws.formzu.net/fgen/S24831117/
※話題提供いただくセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンのアンケート結果がNHK「おはよう日本」でも紹介されました。詳しい状況をお話しいただく予定です。
https://www.nhk.jp/p/ohayou/ts/QLP4RZ8ZY3/blog/bl/pDodEAXj7Y/bp/prLqembzZj/
防災学術連携体は、62学協会から選任された防災連携委員、学識会員、日本学術会議防災減災学術委員会委員各位を対象にWeb研究会(ZOOM)を継続的に開催しています。限られたメンバーによるWeb研究会は、密度の濃い質疑応答とディスカッションを通して、会員間の交流・連携を深めることを目的とします。
このたび、こども環境学会災害復興支援部会は、「震災から復興へーこどもの声を軸に-」と題して、Web研究会を担当することとなりました。
皆様、奮ってご参加ください。
--------------------
■防災学術連携体 第26回Web研究会 こども環境学会
-------
日時:10月13日(日)14:00~17:00
テーマ:「震災から復興へーこどもの声を軸に-」
開会挨拶:米田雅子(防災学術連携体代表幹事)
会長挨拶:木下勇(こども環境学会 会長)
趣旨説明:三輪律江(横浜市立大学)
話題提供:※話題提供の順番を変更しています。
1)「福島県との包括連携協定の歩みー緊急時から中長期にわたる支援ー」谷本都栄(帝京大学)
2)「熊本地震におけるこどもの遊び環境活性化支援活動について」佐久間治(九州女子大学)
3)「災害後のこどもの意見表明ー能登半島地震におけるこどもたちの声を中心にー」安部芳絵(工学院大学)・田代光恵(公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン)
総合討論 「こども環境学として災害復興にどう向き合うか」
タイムテーブル
14:00~14:05 開会挨拶 米田雅子(防災学術連携体 代表幹事)
14:05~14:10 会長挨拶 木下勇(こども環境学会 会長)
14:10~14:35 趣旨説明 三輪律江
14:35~15:05 話題提供 谷本都栄
15:05~15:35 話題提供 佐久間治
15:35~16:05 話題提供 安部芳絵・田代光恵
16:05~17:00 総合討論
■お申込み 参加申し込み締切 10月11日(金曜日)
https://ws.formzu.net/fgen/S24831117/
・申し込まれた方には、Web研究会開始前に、防災学術連携体事務局よりZOOM の招待メールをお送りいたします。
《声明》令和6年能登半島地震に関する声明・こども関連支援情報
令和6年能登半島地震に関する声明
-復旧・復興に、こどもの「遊び」と「参加」をー
令和6年1月1日16:10分頃に石川県能登地方を震源とする最大震度7の地震が発生しました。この震災により亡くなられた方に心より哀悼の意を表します。また、被災されたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。
被災の当事者にはこどもも含まれます。こども環境学会としては、PTSD(心的外傷後ストレス障害)など災害のダメージからの回復には「遊び」やこどもの「参加」が重要であると考えます。
しかし、
・避難所運営は主として成人男性が行うことが多いため、こどもの声が反映されにくい
・災害時にはこどもの遊び場が減少し、遊びは後回しにされがちである点が懸念されます。
そこで、
・避難所運営や復興プロセスにおいては、こどもの声を聴くことが必要であること
・避難所等でこどもの遊び場を確保すること
が重要です。
こども環境学会としては、引き続き災害時の急性期、中・長期的に遊びの提供や遊び場の確保、子ども参加などを働きかけていく予定です。
今後の活動につきましても、随時、ご報告を申し上げて会員の皆さまと情報を共有しますとともに、皆さまの情報提供やご支援も賜りたくお願い申し上げます。
2024年1月3日
公益社団法人 こども環境学会
代表理事 仙田満
会長 五十嵐隆
こども関連支援情報(令和6年能登半島地震支援)
https://www.children-env.org/Education_and_enlightenment/ready_service
地震の発生を受け、過去の震災関係の情報を整備しつつ、こども関連支援情報および関連機関の情報リンクなど順次公開していきます。
防災学術連携体(令和6年能登半島地震)
https://janet-dr.com/050_saigaiji/2024/050_240101_notohantou.html
特設WEBページ 関連団体の発信情報が掲載されています。(こども環境学会の発信情報も含みます)
福島県ふくしま保育環境向上支援事業について
福島県ふくしま保育環境向上支援事業について
福島県とこども環境学会は連携協定を締結して、子どもの環境セミナー事業を実施してきました。
令和2年度に続き、令和3年度も園庭や園舎の改善、遊びの工夫など、こども環境創生の事業計画に対する補助が行なわれるそうです。
詳細は、こちらのホームページをご参照ください。
■子どもの環境セミナー開催
園庭と園舎の設計、ビオトープや自然環境を取り込んだ園庭づくり、非認知能力の育成、マルチメディア活用、子どもの生育環境と心身の健康等について、ビデオ視聴ができます。
■令和2年度こども環境創生事業例 https://kodomo-fukushima.org/route1/
事例として「ロータス保育園」のケースが紹介されています。改修前、当初の改修イメージ、こども環境学会のアドバイス、改修イメージ、改修後、こどもたちが実際に遊ぶ様子も動画で紹介されています。
こども環境学会からの新型コロナウイルスに関する呼びかけ5
新型コロナウイルス感染拡大防止と 子どもの心身の健康のバランス その5
緊急事態宣言のなかでの子育て ~親子あそび~
外出自粛の中、小さなお子さんと楽しく過ごすヒントとして、児童学の専門家、神谷明宏氏(聖徳大学准教授)が、親子遊びを紹介します。
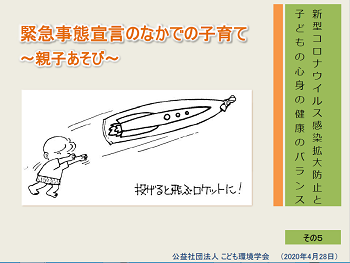
1.不安のあとに安心と喜び
いないいない、ばあ!
2.親子遊びの三要素
スキンシップ・アイコンタクト
・声掛けを含む遊び
3.大人の“遊び心”が大切
4.父親との遊び
こども環境学会からの新型コロナウイルスに関する呼びかけ4
新型コロナウイルス感染拡大防止と 子どもの心身の健康のバランス その4
おうちで手軽にできる遊びのレシピ
ずっと家にいると、子どもは退屈でぐずったり、きょうだいげんかしたり、ママやパパも大変です。ここでは、 乳幼児から小学校低学年児までの子どもにも 手軽にできる遊びを 、「その2 」も執筆した 大豆生田啓友氏 玉川大学教授 が 紹介します。ゲームやスマホ以外になるべく直接体験できる遊びをたくさんしたいものです。ぜひ、参考にしてください。
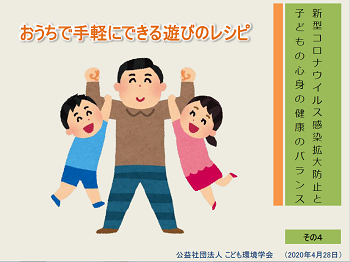
1.描いたり、作ったりして遊ぼう
2.からだを動かして遊ぼう
3.ゲームして遊ぼう
4.お手伝いして遊 ぼう
5.ごっこ遊び・なりきって遊 ぼう
6.外で遊 ぼう
7.絵本を読んだり、作ったりして遊ぼう


